
歯科コラム詳細dental-column
歯科
虫歯治療のすべて|虫歯の症例や予防法を徹底解説!

【この記事の監修歯科医師】
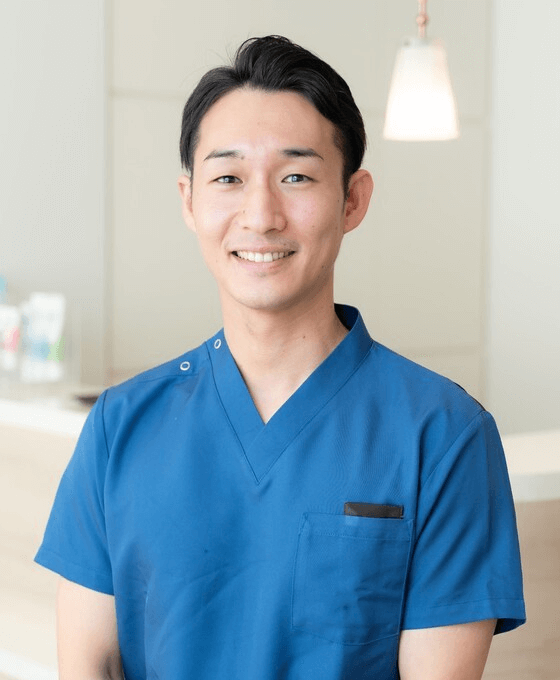
神奈川歯科大学卒業。
公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医。
「再治療のない、丁寧な治療」をモットーに日々情熱を注いでいます。
歯科のお悩みならなんでもご相談ください。
「歯がズキズキ痛む…」「黒い穴ができているけど放置して大丈夫?」
虫歯は放っておくと悪化し、最悪の場合、歯を失う原因にもなります。しかし、早期に適切な治療を受ければ、痛みを最小限に抑え、歯を長く健康に保つことが可能です。
本記事では、虫歯の進行度ごとの症状と治療法、痛みを抑える最新技術、治療費の相場、予防策まで、虫歯治療に関する情報を詳しく解説します。
虫歯に関する疑問を持つ方は、ぜひ最後までご覧ください!
虫歯の基本知識
虫歯とは?原因と進行の仕組み
虫歯(う蝕)は、口の中の細菌が発酵過程で糖(炭水化物)から酸を作り、その酸が歯を溶かしていく(脱灰する)病気です。
虫歯は「細菌」「糖分」「歯の質」「時間」の4つの要素が関係しています。
① 虫歯菌(ミュータンス菌)
- 口の中にいる細菌の一種で、食べ物の糖分を分解して酸を作り、歯を溶かします。
- 歯垢(プラーク)の中に潜み、酸を出し続けます。
② 糖分(食生活)
- 砂糖を多く含む食べ物(お菓子・ジュース・パン・加工食品) は、虫歯菌のエサになります。
- 食後すぐに歯磨きをしないと、酸が長時間歯を溶かし続けます。
③ 歯の質(個人差)
- エナメル質が強い人は虫歯になりにくい傾向があります。(遺伝やフッ素の影響)
- 歯並びが悪いと、歯垢がたまりやすく虫歯リスクが上がります。
④ 時間(口内環境)
- 歯が酸にさらされる時間が長いと、虫歯になりやすいです。
- 唾液が少ないと、口の中の酸を中和しにくくなります。(ドライマウス・口呼吸・ストレスが原因)
虫歯の進行度別の症状と特徴(C0〜C4のステージ解説)
虫歯は進行度によって5つのステージ(C0〜C4)に分類されます。
1. C0
症状:痛みなし、歯の表面が白くなる程度です。
特徴:エナメル質の表面が少し粗造になっている状態です。
2. C1(初期虫歯)
症状:痛みなし、歯の表面が白くなる、エナメル質内に穴があきます。
特徴:エナメル質の表面が少し溶け始めている状態です。
3. C2(象牙質まで進行)
症状:冷たいものや甘いものがしみる、痛みがある場合がある、歯に穴があく、食べ物が詰まりやすいなどの症状がでてきます。
特徴:エナメル質の下にある象牙質まで虫歯が進行
4. C3(神経まで達する)
症状:激しい痛みやズキズキする痛み、温かいものが痛い、冷やすと痛みが落ち着く場合があります。
特徴:歯の神経(歯髄)まで虫歯が到達し、神経の中で炎症が起きます。
5. C4(歯の根まで進行)
症状:神経が死んでしまうため、痛みがなくなることもあります。歯根の周りに膿がたまることや、歯冠がなくなる場合があります。
特徴:歯の根(歯根)まで虫歯が進行し、抜歯が必要になる可能性が高くなります。
虫歯を放置するとどうなる?
虫歯を放置すると、次のような問題が発生します。
- 痛みが悪化する:C2~C3になると冷温痛だけでなくズキズキした痛みが出ます。
- 神経が死んでしまう:C4になると神経が壊死し、一時的に痛みがなくなります。
- 歯が崩壊する:歯がボロボロになり、抜歯が必要になります。
- 歯茎や顎に炎症が広がる:細菌が歯の根や顎の骨に達し、膿がたまります。
- 全身の健康に影響を与える:細菌が血流に乗って、心臓病や脳梗塞のリスクを高めることもあります。
虫歯治療の方法と事例
虫歯の治療方法は、進行度や患者様の希望によって異なります。
虫歯の進行度別の治療法や、痛みを抑えた治療、費用の違い、実際の治療事例を紹介します。
進行度別に選ぶ最適な治療法
虫歯の進行度に応じて、適切な治療法が異なります。
- C0
治療法:フッ素塗布
- C1(エナメル質の虫歯)
治療法:フッ素塗布(初期段階の場合)。虫歯部分の削除+レジン(プラスチック)充填。
- C2(象牙質の虫歯)
治療法:虫歯部分を削り、虫歯の範囲が小さい場合はその場でレジンなどの材料で修復可能です。
虫歯の範囲が大きい場合は詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)で修復します。
- C3(神経に達する虫歯)
治療法:虫歯をとり、根管治療(神経を取り除き、薬を詰める治療)が必要です。根管治療後、被せ物(クラウン)を装着する必要があります。工程が多いので治療回数がかかります。
- C4(歯根まで進行した虫歯)
治療法:虫歯をとり、根管治療が必要です。虫歯の範囲が広い場合は抜歯が必要となります。抜歯後の選択肢によって治療費が変わります。
痛みの少ない治療法:麻酔の種類と無痛治療
虫歯治療の際、「痛みが怖い」「麻酔が苦手」という人も多いですが、最新の麻酔技術や無痛治療の方法を活用すれば、ほぼ痛みを感じずに治療が可能です。
〈虫歯治療で使われる麻酔の種類〉
1. 表面麻酔(塗る麻酔)
- 麻酔の針を刺すときのチクッとした痛みを軽減するための塗る麻酔
- ジェルやスプレータイプで、歯ぐきに塗るだけ
- 針を刺す前に使うことで、ほぼ無痛で麻酔注射ができる
- 表面麻酔+局所麻酔の組み合わせで使われることがほとんどです
2. 局所麻酔(注射麻酔)
- 一般的な歯科麻酔で、治療する部分の感覚をなくします
- 1回の注射で 30分 〜 2時間ほど効果が持続します
- 治療後に唇や頬がしびれることがあるが、数時間で回復します
- 表面麻酔+局所麻酔の組み合わせで使用することで痛みを限りなく無くすことが
できます
3. 伝達麻酔(広範囲の麻酔)
- 神経の根元に麻酔を打ち、広範囲の痛みをブロック
- 奥歯の治療や、抜歯など痛みを感じやすい部位に使われます
- 効果が数時間持続します
4. 笑気麻酔(リラックス麻酔)
- 鼻から吸うタイプの麻酔で、リラックス効果があります
- 眠るわけではなく、意識はあるが不安が軽減されます
- 効果は短時間で切れるため、安全性が高い
- 歯科の雰囲気が苦手な人、強い不安がある人向け
- 治療する部位の痛みを無くすわけではないので、局所麻酔との併用が必要です
5. 静脈内鎮静法(点滴麻酔)
- 点滴で鎮静剤を入れ、ウトウトした状態で治療を受けられます
- 意識はあるが、治療中の記憶があいまいになることが多いです
- 全身麻酔とは違い、呼吸は自力でできます
- 親知らずの抜歯やインプラント治療向け
- 歯科治療に対する恐怖症が強い人向け
6. 全身麻酔(完全に眠る麻酔)
- 意識を完全に失わせ、痛みを一切感じません
- 呼吸管理が必要なため、大学病院や総合病院での処置が中心
- 治療後の覚醒に時間がかかります
- 重度の歯科恐怖症の患者に使用されます
- 大掛かりな口腔手術(顎の手術・多数の抜歯など)に使用されます
〈無痛治療のための最新技術〉
1. 極細針を使用した無痛注射
- 通常よりも細い針(33G〜35G)を使うことで、刺すときの痛みを軽減
- 針が細いほど、神経への刺激が少なくなる
2. 電動麻酔注射
- 一定のスピードでゆっくり麻酔液を注入するため、痛みを感じにくい
- 手動の麻酔注射よりも、違和感が少なくなる
保険適用と自由診療の違い|費用と相場の解説
虫歯治療には「保険適用」と「自由診療」の2種類があり、それぞれ治療方法や費用に違いがあります。
ここでは、両者の違いを詳しく解説し、費用の相場についても紹介します。
1. 保険適用の虫歯治療
公的医療保険が適用されるため、自己負担は1~3割になります。
一般的な虫歯治療のほとんどは保険診療で受けることができます。
治療の特徴
- 費用が安い(3割負担)
- 全国一律の料金(診療報酬制度に基づく)
- 使用できる材料や治療方法が限定される(できる治療が限られる)
- 審美的な要求は基本的にできない(再現できる色味が限られる)
主な治療内容と費用相場(3割負担の場合)(目安)
| 治療内容 | 3割負担の費用 |
| 軽度の虫歯(レジン) | 約1500円 |
| 中程度の虫歯治療(インレー) | 約3000円 |
| 重度の虫歯治療(クラウン) | 約6000円 |
| 神経を取る治療(根管治療) | 約9000円(全体合わせて) |
使用できる材料
| 詰め物 | コンポジットレジン |
| 詰め物(インレー) | 銀歯(Pd)、CAD/CAM |
| 被せ物(クラウン) | 銀歯(Pd、Ti)硬質レジン前装冠(前歯のみ)、CAD /CAM冠 |
2. 自由診療の虫歯治療
公的医療保険が適用されず、治療費は全額自己負担となりますが、審美性や耐久性に優れた材料や最新の治療法を選ぶことができます。
治療の特徴
- 自由に材料を選べる(セラミック・ジルコニアなど)
- 治療の幅が広がる
- 審美性・耐久性が高く、むし歯の再発リスクが低い
- 費用が高額になる
主な治療内容と費用相場
| 治療内容 | 費用相場 |
| MTAセメント | 40,000円〜 |
| セラミックインレー | 30,000~60,000円 |
| ジルコニアインレー | 60,000~100,000円 |
| ゴールドインレー | 40,000~80,000円 |
| セラミッククラウン | 80,000~150,000円 |
| ジルコニアクラウン | 100,000〜200,000円 |
| 根管治療 | 50,000~300,000円 |
虫歯を防ぐために実践したい予防策
日常の予防習慣:正しい歯磨き・フロスのポイント
〈正しい歯磨きの仕方〉
①最初は、鏡を見ながら毛先が届いていることを確認してください。
②動かし方
様々な動かし方がありますが、基本的な動かし方は細かく軽く動かすことです。
歯と歯肉を傷つけることなくプラークを落とすことができれば力は必要ありません。
③力のかけ方
力を入れて磨くと歯ブラシの毛先が開いてしまいプラーク(歯垢)が落とせません。
さらには、歯や歯肉を痛めてしまいます。
力の目安は、毛束がまっすぐなまま歯面に当たる程度です。
④1ヶ所につき10回~20回ほど磨いてください
プラークは粘着性が高いため、2回~3回歯ブラシを動かした程度では落としきれません。
1日に最低1度は、時間(5分以上)をかけてゆっくりと隅々の歯垢を取り除いて下さい。
可能であれば、毎食後磨くことが理想です。
とくに、寝る前に丁寧にゆっくりと磨くことが効果的です。
〈歯磨きの基本ポイント〉
①1回5分を目標に磨く
歯ブラシで時間を測りながら磨くのもおすすめです。
1日最低一度は、5分間かけて磨いてください。
② 1日3回以上
1日3回、朝と特に夜はしっかりと磨きましょう。
特に夜は、寝ている間に細菌が増えやすいため、念入りに磨いてください。
③フッ素入りの歯磨き粉を使用する
歯の再石灰化を促進することで歯を強くします。
④歯ブラシは1ヶ月に1回交換する
毛先が開いたまま磨くと汚れが取れない、歯ぐきを傷付けるなどが起きてしまいます。
毛先が開いた間隔がなくても1ヶ月に1度は歯ブラシを交換しましょう。
〈フロス、歯間ブラシの正しい使い方〉
歯間ブラシとフロスの違い
歯間ブラシとフロスでは、それぞれ用途が異なるため、自身の歯並びや使用する箇所によって上手に使い分けることが大切です。
歯間ブラシ
歯間ブラシは、歯と歯の隙間が広い部分(歯茎に近い部分など、食べかすが詰まりやすい箇所)での使用に適しています。特に、すきっ歯の人や歯周病の影響で歯茎が下がっている人などは、積極的に使用しましょう。
フロス
フロスは、歯と歯の隙間が狭い部分(歯と歯の接した面の汚れが溜まりやすい箇所)での使用に適しています。
特に歯間ブラシが通らない人は、積極的に使用してください。
〈歯間ブラシとフロスの選び方〉
歯間ブラシの選び方
歯間ブラシを選ぶ際に大切なのは、サイズ選びです。
歯と歯の間が広い場合に、小さすぎる歯間ブラシを使用しても、歯垢はなかなか落ちません。一方で、歯と歯の間が狭い場合に大きすぎる歯間ブラシを使用すると、歯茎が下がる原因になったり、歯茎を傷つけてしまったりするおそれがあるため注意が必要です。
はじめて歯間ブラシを選ぶときは、小さいサイズから試してみることをおすすめします。
フロスの選び方
フロスの種類は、大きく分けて以下3つに分類されます。
- ホルダータイプ(F字型)
- ホルダータイプ(Y字型)
- ロールタイプ
F字型のホルダータイプは前歯で使用しやすく、Y字型のタイプは奥歯に使いやすいという特徴があります。
ロールタイプは、太さや形状などが異なるものが数種類あり、清掃力を高めるために唾液に触れると膨らみ、歯と歯の間に密着するタイプなどさまざまです。
ロールタイプは細かい動きが可能であり、力を調整しやすいため、初心者でも使いやすくなっています。
生活習慣、食生活と虫歯予防:セルフケアの工夫
虫歯を防ぐためには、正しい歯磨きだけでなく、食生活や生活習慣の見直しも重要 です。
特に、糖分の摂取や食事のタイミング、唾液の分泌を意識することで、虫歯リスクを大幅に減らせます。
1. 食生活で虫歯を予防する工夫
〈虫歯になりやすい食べ物・飲み物を知る〉
虫歯の原因となるのは、糖分が含まれた飲食物が口の中に長時間残ることです。
- 砂糖が多いお菓子(チョコ、キャラメル、クッキー、飴)
- 清涼飲料水(炭酸飲料・スポーツドリンク・ジュース)
- パン・クラッカーなどの炭水化物(デンプンが唾液で糖に変化)
- ドライフルーツ、チョコバー(歯にくっつきやすい)
〈食事のタイミングを意識する〉
1日の食事回数や間食の取り方も、虫歯予防に影響します。
ダラダラ食べ(長時間、口の中に糖がある状態)や食べた後すぐに歯磨きをしないなどの習慣があると虫歯のリスクが上がってしまいます。
間食は1日1〜2回に抑える(常に飴などを口の中にいれておかないなど)、時間を決めて食べる、食後に歯を磨くなどの習慣をつけることが大切です。
2. 唾液の分泌を増やす習慣
口の中を潤している唾液には、口内の汚れや細菌を洗い流す自浄作用や、細菌の発育を抑える抗菌作用、口の中の酸を中和し歯の再石灰化を助けるなどの役割があります。
唾液の分泌の減少は、これらの働きが減少してしまいます。
唾液を増やす方法
- よく噛んで食べる
噛むことで唾液腺が刺激されて、分泌が活発になります。
ガムを噛むのも効果的です。
- 水分を補給して口の中を潤す
ただしカフェインには利尿作用があり、水分が排出されてしまうので、
水分補給にお茶やコーヒーはおすすめしません。
- 鼻呼吸を心がける
口呼吸は口腔内を乾燥させます。
- 唾液の分泌を促進させる食べ物
レモンや梅干しなどのすっぱいものが代表的ですが、昆布に含まれるアルギン酸や納豆のポリグルタミン酸も唾液の分泌を促進します。
また、セロリやニンジン、アーモンドなども唾液の分泌を促します。
- 唾液腺マッサージをする
唾液腺は、おもに3つあります。
・舌下腺顎先の内側の少し凹んだ部分を親指でくるくると押しましょう。
・顎下腺エラの張った部分の内側の少し凹んだところを、親指でくるくると押しましょう。
・耳下腺耳の穴の斜め下のあたりをくるくると押しましょう。マッサージすると唾液腺が刺激されて、唾液の分泌が促されます。優しく刺激するようにしましょう。
フッ素とシーラントの効果的活用法
フッ素の効果的な活用法
フッ素は歯を強化し、酸による脱灰を抑えることでむし歯予防に役立ちます。
1. フッ素入り歯磨き粉を使用する
- 選び方: フッ素濃度が1,000ppm以上のものを選ぶ(子どもは年齢に応じた濃度を使用)
- 使い方: 適量を歯ブラシに取り、しっかりブラッシング(うがいは最小限に)
2. フッ素洗口を取り入れる
- 学校や家庭でのフッ素洗口(低濃度のフッ素溶液で口をすすぐ)を習慣化すると効果的です。
3. 歯科医院でのフッ素塗布
- 高濃度のフッ素を定期的(3~6ヶ月ごと)に塗布すると、むし歯予防効果がさらに高まります。
シーラントの効果的な活用法
乳歯または生えたての奥歯は溝が深く、むし歯になりやすいので奥歯には「シーラント」がおすすめです。
シーラントは、奥歯の溝を埋めることで食べ物をつまりずらくし、むし歯を防ぐ治療法です。
1. 適用部位を選ぶ
- 乳歯の奥歯、生えたての永久歯の奥歯の深い溝がある部分(特に6歳臼歯や12歳臼歯)にシーラントを施すと、むし歯予防効果が高いです。
2. 定期的にチェックする
- シーラントは摩耗や剥がれることがあるため、歯科検診で状態を確認し、すり減りなどがみられた場合、再処置を行う必要があります。
3. シーラント後も歯磨きを怠らない
- シーラントをしても、むし歯を完全に防げるわけではないため、フッ素と併用しながら歯磨きを徹底しましょう。
定期検診の重要性と早期発見のメリット
1. 定期検診の重要性
歯の健康を維持するためには、毎日のセルフケアだけでなく、歯科医院での定期検診が不可欠です。定期検診を受けることで、以下のようなメリットがあります。
虫歯や歯周病の予防:歯科医や歯科衛生士による専門的なクリーニング(スケーリング)により、歯垢や歯石を除去し、虫歯や歯周病を防ぎます。
- 口腔環境の改善:噛み合わせのチェックや、歯の磨き残しが多い部位の指導を受けることで、口腔内を清潔に保ちやすくなります。
- 全身の健康維持:歯周病は糖尿病や心血管疾患など全身の病気とも関係が深いため、口腔の健康を保つことが全身の健康にもつながります。
2. 早期発見のメリット
定期検診では、初期段階の問題を発見し、早期に対処することができます。早期発見のメリットには以下のようなものがあります。
- 痛みを感じる前に治療できる:初期の虫歯や歯周病は自覚症状が少なく、痛みを感じる頃には進行していることが多いです。早期に発見できれば、痛みを伴う治療を避けられます。
- 治療費の負担が軽減できる:初期段階で治療すれば、治療範囲が小さく済み、費用も抑えられます。進行すると、詰め物や被せ物、場合によっては抜歯やインプラントが必要になり、費用が高額になります。
- 歯を長く健康に保てる:早期に問題を発見・治療することで、歯を削る量を最小限に抑え、自分の歯をできるだけ長く保つことができます。
3. 定期検診の頻度
一般的に、3~6ヶ月に1回の定期検診が推奨されます。
特に歯周病のリスクが高い人や、過去に大きな治療を受けたことがある人は、より短い間隔で受診することをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
虫歯は自然に治る?
虫歯は自然に治ることはありません。進行すると悪化し、放置すれば歯を失うリスクもあります。
しかし、ごく初期の虫歯(C0)であれば、適切なケア(定期検診、フッ素塗布など)
によって進行を防ぎ、再石灰化させることが可能です。
治療後に痛みが続く理由と対処法
虫歯治療後に痛みが続くことがあります。これは治療の種類や歯の状態によって異なります。
治療後の痛みの主な原因
| 痛みの原因 | 症状の特徴 | 対処法 |
| 詰め物・被せ物の違和感 | ・噛むと痛みや違和感がある | ・噛み合わせの調節 |
| 神経の過敏反応(C2の治療後) | ・何もしなくても少し痛い・冷たいものが染みる | ・治療直後の場合は経過をみる場合が多い ・長期間続くようであれば神経の処置が必要なこともある |
| 根管治療後の炎症(C3の治療後) | ・じんじんした痛み ・噛むと痛い ・何もしていなくても違和感がある | ・基本的には数日で落ち着くが悪化する場合は再受診が必要 |
| 抜歯後の痛み | ・何もしなくても痛い | ・鎮痛剤の服用 |
治療期間や通院回数について
虫歯の進行度や治療方法によって、通院回数や期間は異なります。
進行度別の治療回数目安
| 進行度 | 治療法 | 通院の目安 |
| C0 | フッ素塗布 | 1回 |
| C1 | フッ素塗布 | 1回 |
| C2 | レジン充填・詰め物(インレー)被せ物(クラウン) | 1回〜2回 |
| C3 | 根管治療詰め物(インレー)被せ物(クラウン) | 3回以上 |
| C4 | C3と同じ処置抜歯+欠損補綴(Br、義歯、インプラント) | 3回以上 |
当院は大倉山駅から徒歩1分でアクセスも良く、実績も豊富です。口腔外科専門医の資格を持った医師が治療を行いますので安心して治療をお受けいただけます。
まずはお気軽にご相談ください!
